リモートワーク、オンラインゲーム、スマートフォンのWi-Fiなど日々の仕事や暮らしで安定して高速な光回線が求められています。
光回線を選ぶなら、「NTT西日本品質」という選択を。
更新日:2025.10.30
連載ネットの知恵袋 ネットの疑問あれこれ
BIツールとは? 基礎知識から選び方、活用方法までご紹介!

みなさんはBIツールという言葉を耳にしたことがありますか?
BIツールとは、企業がデータを取り扱うために利用するツールです。この記事ではBIツールの基礎知識から機能、活用方法、選び方を紹介しますね。
- <目次>
- 1. BIツールとは?まずは基礎知識からご紹介!
- 2. BIツールにはどういった機能があるの?
- 3. BIツールを使う上で重要なことは?
- 4. BIツールの選び方や活用方法!
- 5. 最新のデータを10G回線で素早く共有!
1BIツールとは?まずは基礎知識からご紹介!
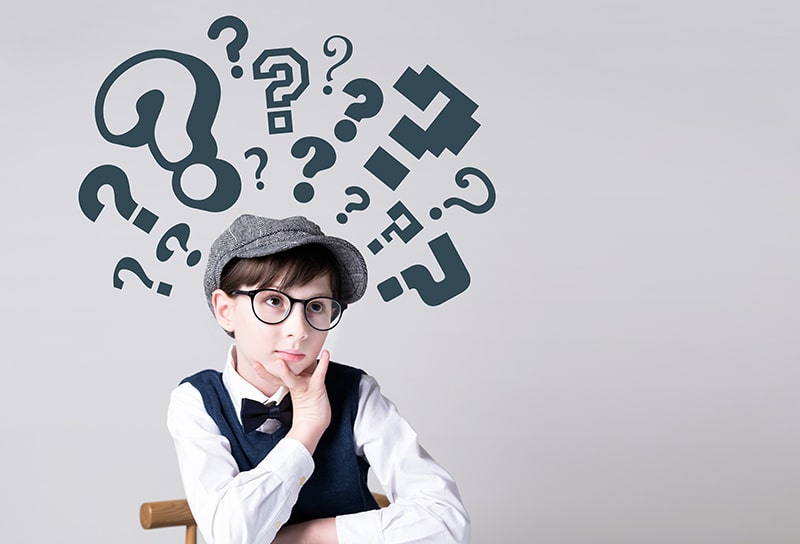
BIツールとは『Business Intelligenceツール(ビジネス インテリジェンス ツール)』の略称で、企業が持つさまざまなデータを収集・分析・可視化することができ、データに基づいた企業の戦略的な判断を支援するツールです。データは『21世紀の石油』とも呼ばれており、世界的にもデータの価値は非常に高いと言えるでしょう。そして、BIツールは企業が蓄積した膨大なデータを一元管理でき、グラフやダッシュボードなどにすることで視覚的にも理解しやすくなるため、注目されています。
今までは、さまざまなデータがある場合、それぞれのデータを分析・統合し、その結果を一つの資料としてまとめるか、データ自体を加工し、統一してから分析するという流れが一般的だったでしょう。しかしながら、BIツールの登場により、今まで複数の工程に分かれていた作業も一つのツールに集約されるため、一括で処理が可能になるということです。
専門知識を持った一部の担当者に任されがちなデータ分析ですが、BIツールを使えばだれでも直感的な操作でデータを分析できる点が魅力です。
さらには生成AIを搭載したものも登場しており、より業務の効率化を図るものもあります。
生成AIについては、次の記事で詳しく書いているため、よければ見てくださいね。
■「生成AI」とは? 従来のAIとの違いや便利な使い方と注意点
https://flets-w.com/chienetta/technology/atr_what-is-generative-ai.html
次に、BIツールにはどのような機能があるのかを紹介していきますね。
2BIツールにはどういった機能があるの?

BIツールの機能はツールごとに異なり、提供元が重視している内容により大きく変わります。そのため、ここでは多くのBIツールに搭載されている、代表的な機能を解説しますね。
・レポート生成
日次・週次・月次のデータを自動で計算し、レポートを生成する機能
必要なデータ(CSVファイルなど)を指定のツールで読み込み、グラフや表を手作業または自動で作成してレポートにまとめる作業を、定期的に自動で行ってくれるため、業務効率が大幅に向上します。
・データ統合
複数のシステムやデータベースから情報を集約する機能
手作業で整えていたデータ項目や形式の統一・加工・統合を自動で行ってくれるため、業務効率が大幅に向上します。
・ダッシュボードの作成
さまざまなデータの分析結果をリアルタイムで表やグラフにまとめ、可視化する機能
担当者が定期的にデータを分析し、手作業で表やグラフにまとめ、会議などで報告していたものを自動で作ってくれるため、業務効率が大幅に向上し、進捗状況もリアルタイムで確認ができます。
・OLAP分析
多角的な視点からデータを分析する機能
例えば、「性別」「年代」「地域」などの条件を加味した売上データを分析することができ、顧客傾向などの商品や提供サービスの品質以外の要素を深く理解できます。
・データマイニング
大量のデータから、これまで気づかなかったパターンなどを自動で発見する機能
単なるデータの集計や可視化とは異なり、未来の予測や新たな法則の発見を目的とするため、トレンドや顧客の購買行動などの予測を可能にし、新たな可能性を生み出します。
いくつかの機能を紹介しましたが、BIツールによって機能はさまざまです。
レポート生成に特化したものもあれば、OLAP分析やデータマイニングなど、企業戦略の立案を支援することに特化したものもあります。
ここで挙げた機能を活用できれば、BIツールの性能を十分に発揮し、経営を支える重要な存在になりえるといっても過言ではないでしょう。また、リアルタイムでレポート生成やデータマイニングをしてくれるため、ビッグデータとの相性は非常に良く、今まで気づけなかった情報についてもBIツールとビッグデータによって手に入るかもしれません。
ビッグデータについては他の記事で紹介しているので、よければ見てくださいね。
■基本を解説!暮らしと身近なビッグデータ インターネットとの関係は?
https://flets-w.com/chienetta/technology/nrt_ser-cat36_big-data-around-us.html
次に、BIツールを利用する上で重要なことを紹介しますね。
3BIツールを使う上で重要なことは?

BIツールは導入するだけで効果を期待できるようなものではありません。導入する際は、次の点に注意して検討しましょう。
・目的の明確化
『業務の効率化による人件費の削減』や『分析結果に基づいた営業による目標水準の向上』など、利用者によってさまざまな目的があると思います。その目的に沿った機能が備わったBIツールを選ぶと良いでしょう。
・データの整備
正確で一貫性のあるデータを用意することが重要です。BIツールはデータを分析し、予測を立てるなどして役に立ってくれるツールです。元となるデータに誤り、重複、欠損などがあると分析や予測が間違ったものになる可能性が高いです。逆に正確で膨大なデータがあると詳細な分析や予測ができるようになります。
・ユーザーの教育
BIツールの使い方や分析の考え方、および分析結果の見方をしっかりと理解することが大切です。BIツールに限ったことではありませんが、新しく便利な技術については学習が必須になります。
便利な機能であればあるほど学習は重要ですが、慣れてくると業務効率が向上しているでしょう。
・小規模での開始
特定の部署などから小規模でスタートしてみましょう。いきなり全社で始めるのではなく、まずは特定の部署からスタートし、トライアル期間を設けることで、課題を事前に把握できます。ここで課題が見つかれば本導入前に調整が可能になり、全社で導入する際によりスムーズかつ適切な状態で導入を進めることができるでしょう。
・継続的な改善
使いながら課題を見つけて改善に取り組むこと。小規模で開始する際の延長線上になりますが、多機能が故に最初からユーザーの希望に沿った設定になっているわけではありません。実際に使ってみた際に希望に沿った設定に見えても、より希望に近づける設定が可能な場合もあります。
重要なことが多くて少し混乱してしまうかもしれませんが、一言でまとめるなら、「正しいデータを、正しく活かす!」ということに尽きます。この言葉だけ覚えていただければ、BIツールの本質はしっかり押さえられています。
「データの整備」と「ユーザーの教育」以外については、何かを導入する際に共通して求められる重要なことだと思います。次はそんなBIツールの選び方や活用方法を紹介しますね。
4BIツールの選び方や活用方法!
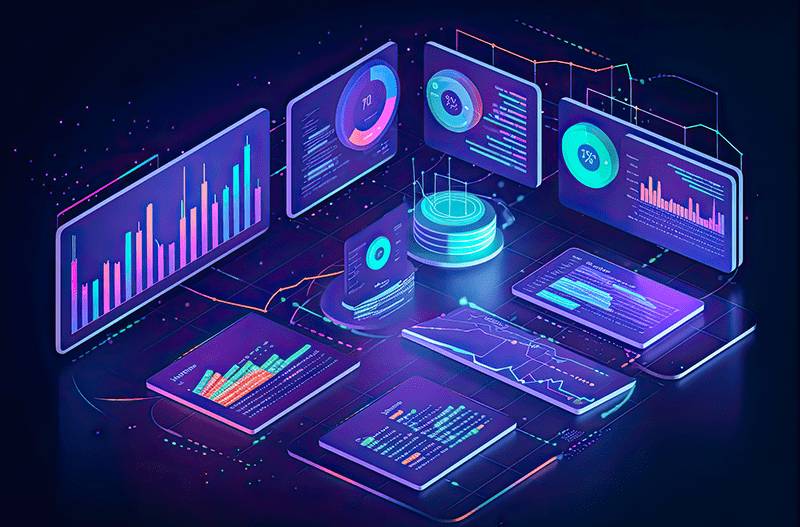
BIツールを選ぶ際は、以下の基準に沿って選ぶことが大切です。
① 操作性
最初に確認するべき内容となります。なぜなら、現在使っているツールより操作工数が多いと目的の一つである業務効率化と真逆になるからです。また、ユーザーが使いにくいと感じてしまうと逆効果になるので、まずは操作しやすいか、見やすいかなどのユーザー目線で考えましょう。
② 利用環境
オンプレミス型・クラウド型のどちらを希望するかを決めましょう。オンプレミス型とは、自社のサーバー上にシステムを構築して利用する方法になり、クラウド型は提供元の管理するサーバー上で構築されたシステムを利用する方法となります。数十年前はオンプレミス型が主流でしたが、光回線の普及や通信速度の向上に伴い、クラウド型も今や一般的な提供スタイルとなっています。
また、提供方法だけではなく、既存で利用しているシステムが流用できるかの確認もしましょう。
この利用環境の確認は、提供元に問い合わせるのが確実です。
③ セキュリティー
データは『21世紀の石油』と呼ばれるほど、非常に価値のある資源です。膨大なデータであればあるほど、詳細かつ有用な情報を生み出す可能性があるため、データの取り扱いには細心の注意を払う必要があります。そのため、堅牢なセキュリティー対策が施されているか確認することは重要です。
④ コスト
当然のことですが、初期費用とランニングコストは導入時に重要なポイントです。
利用環境でも少し触れましたが、BIツールには「オンプレミス型」と「クラウド型」があり、それぞれ費用の構造が大きく異なります。
一般的に、オンプレミス型は初期費用が高く、ランニングコストは比較的安価です。一方、クラウド型は初期費用が抑えられる反面、月額利用料などのランニングコストが高くなる傾向があります。例えるなら、「商品を一括購入するか、月額でレンタルするか」の違いです。
また、同じような価格帯のBIツールでも、提供元によってサポート体制やマニュアルの充実度が異なるため、実質的なコストパフォーマンスにも差が出ることがあります。導入時には、価格だけでなく、サポートの質や使いやすさも含めて総合的に判断することが大切です。
BIツールの選び方についてはいかがでしたか?これらの基準をもとに最適なツールを見つけることができたら、次はそれをどう活用するかが重要になります。
① データ集計・分析の自動化と効率化
手作業で行っていたデータの収集や集計を自動化し、作業時間を大幅に削減します。これにより、担当者は単純な作業から解放され、データが示す傾向や課題の分析という、より本質的な業務に集中できるようになります。
② 経営判断の迅速化
リアルタイムで可視化するダッシュボードを作成できるため、最新のデータを一目で把握し、市場や顧客の変化に合わせて根拠に基づいた迅速な意思決定が可能になります。
③ チーム間でのデータ共有と連携
作成したレポートや分析結果を簡単に共有できるため、部署やチームが同じデータをもとに議論を行えるようになります。これにより、認識のズレを防ぎ、部門を越えた共通の目標達成に向けたスムーズな連携が生まれます。
このように、BIツールは業務の効率化から経営判断の迅速化まで、さまざまな場面で力を発揮します。総務省が運営する『Data StaRt』は、地方公共団体向けのデータ利活用支援サイトであり、各自治体がBIツールを活用した事例を多数紹介しています。
たとえば、「統計データ利活用事例集」では、人口統計や地域経済に関するデータをBIツールで可視化し、子育て支援政策の立案や地域活性化策の検討に活かした事例が掲載されています。
▼統計データ利活用事例集
https://www.stat.go.jp/dstart/case/download.html
最初に確認すべきポイントは操作性となりますが、その他の項目についても無視できない内容となるため、導入を検討している場合は活用方法も踏まえて、じっくりと考えましょう!
5最新のデータを10G回線で素早く共有!

BIツールの導入が進むと、膨大なデータが日々生成され、分析レポートも増えていきます。ここでボトルネックとなりがちなのが、通信速度です。
最新のデータをリアルタイムで共有できる仕組みができたら次は回線の通信速度の向上を目指してみてはいかがでしょうか?
各社でさまざまな10G(ギガ)回線のプランを出しており、例えばNTT西日本では、最大概ね10G(ギガ)※1の「フレッツ 光クロス※2」を提供しています!
また、NTT西日本から光回線を借り受けてサービスを提供している一部の光コラボレーション事業者の「コラボ光」からも最大概ね10G(ギガ)スペックのサービスが提供されています。
高速で安定性を追求したインターネットを提供するNTT西日本品質なら、大容量通信の環境を快適に過ごすことができるため、快適な通信環境にしたい方などにおすすめです。※3「フレッツ 光クロス」の利用を検討されている方は「フレッツ 光クロス」がお住まいのエリアで利用できるか「提供エリア検索」で調べてみてくださいね。
※1 ・技術規格上の最大値であり実効速度ではありません。通信品質確保などに必要なデータが付与されるため、実効速度の最大値は技術規格上の最大値より十数%程度低下します。
・通信速度は、端末機器の仕様などお客さまのご利用環境や回線の混雑状況などによって低下します。
※2 フレッツ 光クロスは一部サービスがご利用いただけません(セキュリティ対策ツールなど)。
詳細は[https://flets-w.com/service/cross/service_menu/]をご確認ください。
※3 インターネットのご利用には、プロバイダーとの契約・料金が必要です。
※この記事は2025年9月4日現在の情報です。
NEW最新記事
あなたのお気に入りリスト
あなたが最近読んだ記事
審査25-481
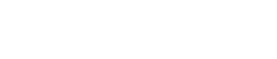
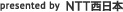
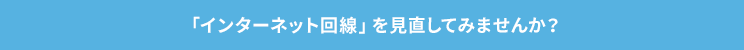
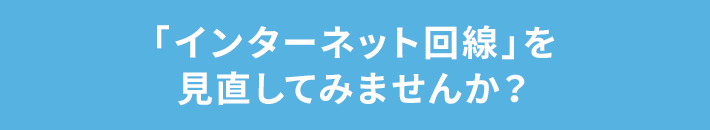
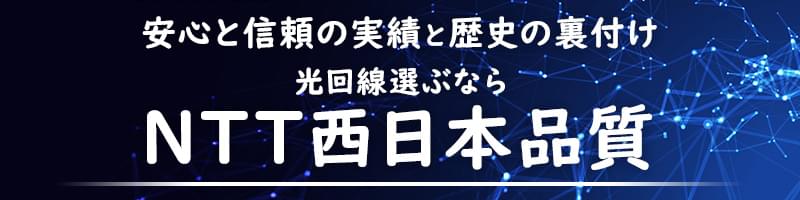
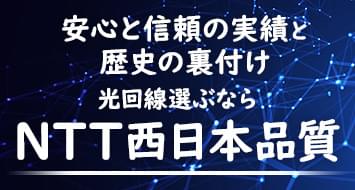
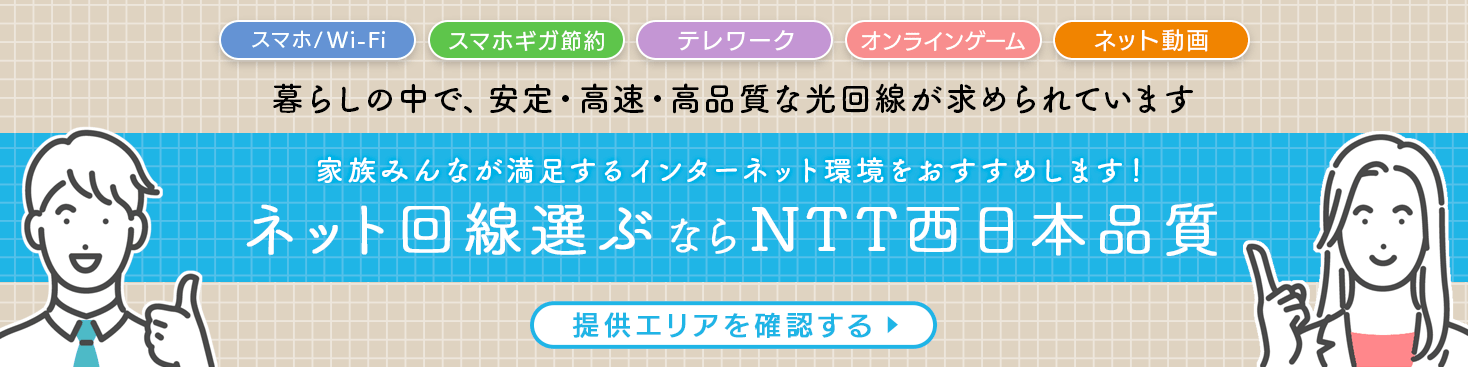
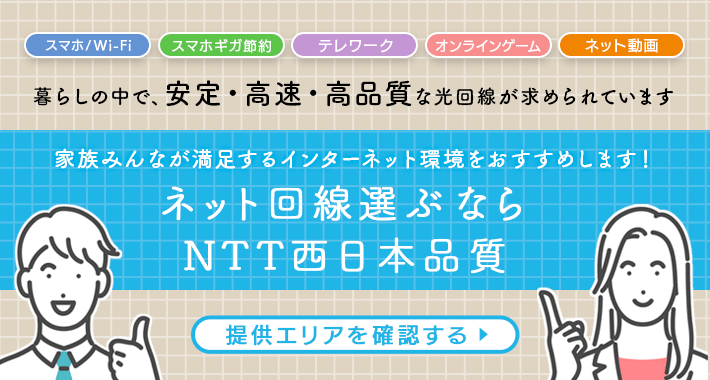

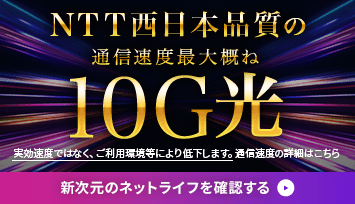









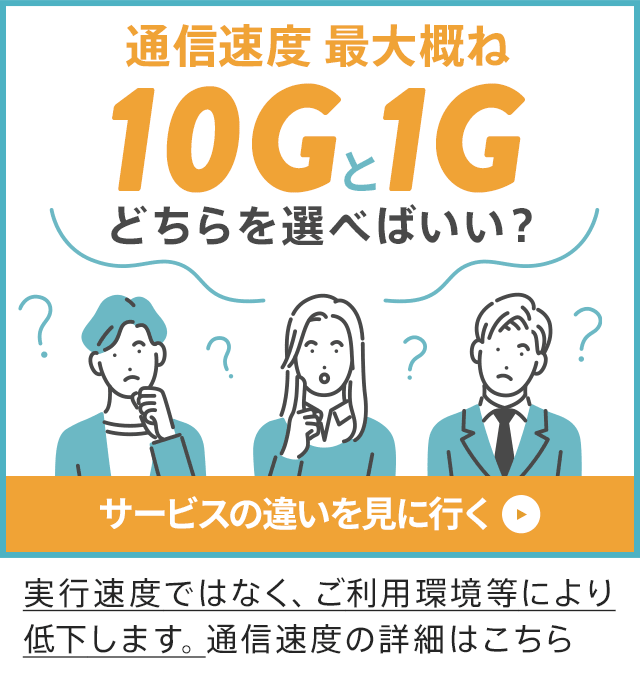




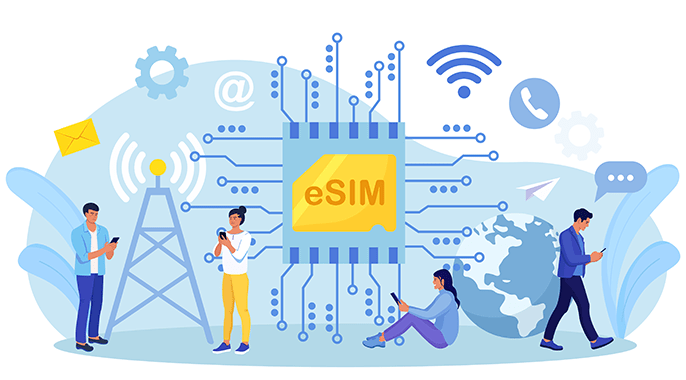



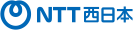

Wi-Fiを使うには? 自宅でWi-Fiに接続する方法と機器...
PC・スマホ/2024.04.10